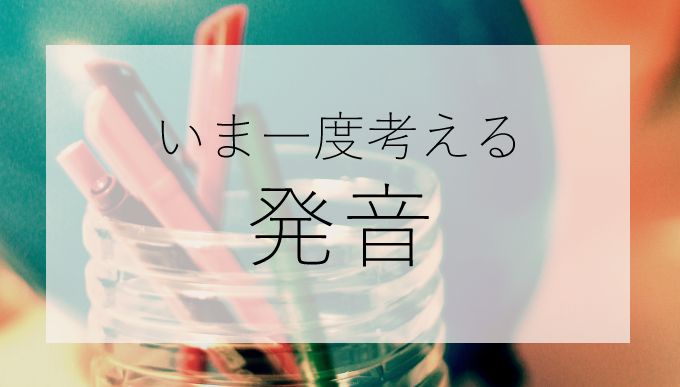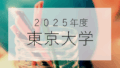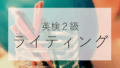こんにちは。TOEIC985点講師のわたらせです。今日は上記のようなテーマで記事を書いてみたいと思います。
日本人が英語を学習するとき、必ずと言っていいほど大きな課題としてついて回ってきた「発音」。
発音を学習しようと思っている方や、現在まさに学習中で苦労している方も多いのではないでしょうか。そこで、質問です。
あなたはなぜ、発音を学ぶのですか?
この記事では、発音がなぜ大事なのかや、日本人が目指すべき発音の在り方について考えていきます!
特に、現在発音を学習中だったり、これから学び始めようという方には、発音について考えるきっかけにしていただければ幸いです。
日本人が話す英語
私たち日本語話者が使っている英語は、「グローバル英語」と呼ばれることがあります。
同じく第二言語として英語を学んでいるスペイン語話者が使っているのも「グローバル英語」ですし、中国語話者が使っているのもインド人が使っているのももちろん「グローバル英語」ということですね。
このグローバル英語が使われる世界では、発音そのものよりもまず「発言すること」が評価されるように思えてなりません。
もしあなたがイタリア人と話せば、「evening」いう単語の発音は「イーブニング」になり、メキシコ人と話せば「card」という単語の音は「カルド」になるかもしれません。フランス人だったら、「history」が「イストリー」のように聞こえるかもしれません。
しかし、そんな発音がハチャメチャな人たちが実際に英語を使ってグローバルな活躍をしています。国際的に活躍する起業家も、政治家も、スポーツ選手も、映画監督も、みんな上記のような「自分たちの国の英語」を使って仕事をしています。
そこで、発音を学びたい人にまず考えていただきたいこと。それは、
すでにこんなにも多種多様なグローバル英語が存在する世界で、忙しいあなたが限られた時間とお金を使って発音をたくさん勉強する意味ってなんでしょう?
ということです。
「そんなの当たり前。自分はアメリカ人みたいにハキハキかっこよく喋りたい!」という確固たる目標がある方は、もちろんその定めたゴールに向かって突き進んでいただきたいと思いますし、ここから先の話は余計なお世話になってしまうでしょう。
でも、もし「え?なんで発音なんだっけ?」と少しでも立ち止まる人がいたら、ぜひこの先を読んでみてほしいのです。
「発音は気にするな」という人たち
「文法や発音なんてどうでもいいから、とにかく話せるように!自分の意見を言えるグローバル人材を育てることを最優先すべき」
近年、教育現場でよく見かける言説です。
これって、どうですか?
誰もが文法や発音を、楽しくてやりたいから勉強しているわけじゃないですよね。それに、みんなの前で堂々と意見が言えるなんていうことは、英語だけではなく教育界全体の課題だと筆者は思うのです。
むしろ多くの人にとって、「発音の勉強ってやっぱり必要だよね」と思うきっかけは、以下のようなことなんじゃないでしょうか。
- 自分の英語が、なかなか人に聞き取ってもらえない
- リスニングができないから、ネイティブの正しい発音を知りたい
確かに、自分の話す英語が伝わらず、相手から何度も聞き返されてしまうのはお互いにとってストレスですよね。それに発音を理解することでリスニング力が上がるならば、自分の知りたい情報を聞き逃すことはなくなります。
突き詰めてみると、これらは全部「コミュニケーション(情報伝達、意思疎通)」に通ずる動機なんです。
ここに挙げた理由でなくても、あなたが「発音を学びたい」と思うその根底にはきっと、「相手が誰であれ、その人の話をしっかり聞いて、そのうえで自分のこともちゃんと伝えられるようになりたい」という気持ちがどこかで共通していると思います。
この「今よりもいいコミュニケーションをしたい」という思いは決して、多種多様を極めるグローバル英語の価値観に相反するものではないと思います。
発音を勉強することでこれからコミュニケーションの質を上がるとしたら、発音を学ぶことにも意味がありそうです!
さあ、ここで次の質問です。
コミュニケーション上手になりたいあなたが目指すのは「どんな発音」でしょうか?
「アメリカ人のような」発音?
英語の発音といえば、appleを「ェアッポー」と読んだり、girlやworldなどのRの音を「巻き舌で強く音を出したりすること」、と最初に思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。
これらは主に、アメリカやカナダで使われている英語の特徴です。
最近はTOEICやTOEFLなど、世界各地の英語を折り混ぜて出題するテストも多くなってきていますが、多くの大人が学生の頃から使ってきた教材の多くはこの北米地域の発音でした。
なので、「英語を勉強していたら結果的にアメリカ人のような発音になっていた」というケースはとても自然に考えられますし、また世界中多くの人が勉強していることを考えると、人に伝わりやすい英語になっていると言えると思います。
しかしそのように自然に習得したものではなく、「アメリカ人のような発音をあえて目指す」ケースにはちょっとした落とし穴があります。それは…
「アメリカ人っぽい発音」を意識しすぎるあまり、逆に他の人にとって聞き取りづらい英語になってしまっている人が残念ながら日本人の中にも一定数存在するということです。
ひとりよがり発音の危険性
「音を伸ばすときにとにかく巻き舌にしておけば、英語がうまく聞こえる」
「カタカナにならないよう、なるべく早口で音を繋げて話すとネイティブっぽい」
もしあなたがこのような考え方をしている場合は、少し立ち止まって考える必要があるかもしれません。
発音の知識や、正しい音の蓄積が自分の中にあればいいのですが、なんとなくでネイティブっぽさを追求してしまうと、結局周り回って「伝わらない英語」に陥っているケースがよくあるのです。
このような場合、話をする相手が英語圏のネイティブスピーカーであれば、意外と困ることがないかもれません。それは、文脈や使っている単語からも、その人が話そうとしている内容を汲み取る力が、ネイティブの人達にはあるからです。これは私たちが、日本語であれば幼児のつたない言葉もある程度汲み取れることからもわかると思います。
しかし、ビジネスや国際交流の場において、英語圏の人だけにあなたの英語が伝わればいい、という考え方は少々乱暴ですよね。どうせ身につけるなら、非英語圏、つまりグローバル英語を使う人たちにも伝わる英語を学んだほうがいいような気がしませんか。
実際、筆者は「r以外の普通の母音でも舌を巻いて」「アメリカ人のような早口で話す」日本人と会ったことがあります。その人は自分の英語にとても自信があり、それ自体はすばらしく良いことだと思いました。しかし発音は全体的に不明瞭で聞き取りづらく、周りにいた私や韓国から来た人はコミュニケーションを深掘りするのに少し苦労してしまったのです。
独りよがりから、おもいやり発音へ
とても当たり前のことですが、私たちが日本語を話すとき、相手によって話すスピードや使う言葉、声のトーンを変えますよね。
幼い子供や耳の遠いご老人には一つ一つの言葉をゆっくりはっきり話すようにしますし、逆に近しい友人なら全体的に言葉が繋がって聞こえるような早口で話しても楽しく会話が進みます。
もし、コミュニケーションをとることを目標にして英語を勉強しているのならば、英語においてもやはり同じように相手のことを考え、思いやった伝え方をしようという姿勢がまず何よりも大事なのではないでしょうか。
正直なところ、発音の学習はその心構えができてからでも遅くはないと思います。
では、そのような心構えを持っていよいよ英語の発音を学ぶ段階になったとき、いったい何を意識すれば誰にでも伝わりやすい英語になるのでしょう。
伝わりやすい発音の条件
これについて筆者は、以下のように条件を考えています。
- 子音の発音が正しく明快である
- センテンス全体が英語らしいリズム、抑揚で話されている
これらが整っていれば、どこの国の人にも話が伝わるのではないかと思います。逆に、どれだけ「r」の舌を巻くのがうまくても、それ以外の子音が滅茶苦茶だったら、あるいはリズムや抑揚が日本語のカタカナを話すときのようにカチコチで一定だったら、やはり聞いている人にはある程度の負担を強いると思います。
「発音の条件」と言っておきながら、実際に必要な音の勉強は子音だけで、むしろリズムや抑揚など、文章全体の話し方が重要と考えている点が意外だったかもしれません。
実際筆者は、アメリカ人からは「イギリスにいたことある?」、イギリス人からは「アメリカ英語?それともオーストラリア英語?」と言われるような、どっちつかずの発音、まさにグローバル英語を使っています。
でも、世界各地の旅行先で英語が通じなかったことはほとんどありません。むしろどの国の人も、あなた英語うまいね!と褒めてくれるのです。それは、筆者の英語が基本的な子音やリズム、抑揚のポイントを押さえているからなのではないかと考えています。
あまりにも記事が長くなりすぎてしまうので、今回は子音やリズムといった個々の内容について詳細に触れることは難しいでしょう。ですがかわりに、ここまで読んできてくださった方にぜひ見てみていただきたい動画があります。
それは、タレントのタモリさんが複数のエセ外国語を操っているというコメディ映像の一幕です。
タモリさんは、それぞれの言語を話せるわけではありません。もちろん単語や文法を知っているわけでもありません。
それでも、リズム、抑揚、それに特徴的な子音の音を巧みに操り、さもその言語を話しているかのように見せることができるのです。
「発音を学ぶ」とは、あるいは「その言語らしい発音を体得する」とは、まさにそのような複合的な要素を学ぶことにほかなりません。
まとめ
世界には「water」を「ワラー」と読む人もいれば、私たち日本人と同じように「ウォーター」と言う人もいます。
大切なのは、「いまのままでは伝わらないな」と気付いたときに、相手のことを思いやった工夫をすることができるか。あくまでもその中の要素の1つが発音なのであり、広いグローバル英語の世界で私たちが持っているべき発音学習の考え方なのではないでしょうか。
最初に「とにかくスピーキング力を!」と喧伝している教育界についても触れましたが、筆者個人としては国際的な場で英語を話そうとすることと、発音を大切にすることは決して相反する考え方ではありません。「伝える力」という点において、どちらか一方のみをとらねばならないというものではないと思っています。その一方で、ネイティブらしい発音ばかりに気を取られて、本当に大事なことが見えなくなってしまってはもったいないと思います。
あなたがもし発音を学ぼうと思っているなら、あるいはすでに学んでいる最中なら、「なぜ発音を勉強するのか」という出発点をぜひご自身でも一度考えてみてください。