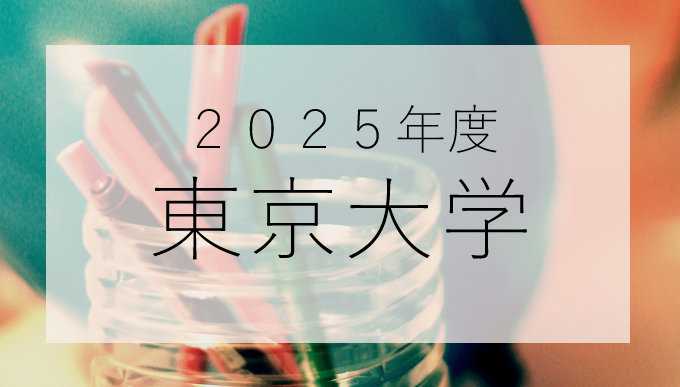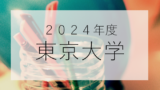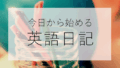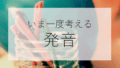2025年度 東大英語の解説です。
今回は大問1 (A)を、パラグラフリーディングで長文読解していきます!
長文の読み方の基礎を確認しながら、じっくり読んでいきます。
- 解答例だけささっと確認したい人
- 単語・文法力不足で、そもそも正確に英文が読めない人
には適さない内容となりますが、逆に
- 日本語訳はできるけど、なぜか問題が解けない人
- 長文読解を極めたい人
など、長文読解を得意にしたい場合はぜひ腰を据えて取り組んでみてください!(そもそも英文の日本語訳ができないという方はこちらの勉強法をCheck)
著作権の関係上、問題そのものは載せていません。インターネットで過去問を手に入れてもいいですし、赤本があれば読みづらかった文法箇所も全訳でチェックできるので、そちらを用意してもOKです!
▶外部サイト:Amazon「東大の英語25カ年[第12版] 」
問題は手元に用意してもらえたでしょうか?それでは解説ノートを見ていきましょう。
2025年度 東京大学 英語 大問1 (A)
◎大問1(A)のキホンの考え方:段落ごとの内容・キーワードを見抜く!
→段落ごとに内容を掴んで読むと、
・要約なら…減点につながる情報の過不足をなくすことができる
まずはパラグラフリーディングを駆使して、ざっと長文の内容を通しで読んでいく。いったん理解してしまえば、読み終わった段階で書くべき内容が決まっているはず!
ただ、今回の英文は内容自体はかなり読みやすく、むしろ「何をどこまで盛り込むか」が答案作成のカギとなる。
といってもただ漫然と自分でうまいこと配分できればよいというものではなく、作者が何を重要視しているのか、その意図を正しく掴む必要がある。
今回は第3段落と、第4〜5段落の読み取りが差のつくポイント。特に、第3段落の使い方と、第4〜5段落のまとめ方に悩んだ学習者も多かったのではないだろうか?(第3段落を完全に無視したK合のような答案も多そうだ…)
当たり前だが、日本一の東大の問題は、よく練られている。当然、どの段落にもそれなりの意味はあるので、しっかり読み取った上で要約に落とし込もう!
第1段落
ものすごく明快な譲歩・逆説の構造だ。これに気づけず読み流す東大受験生はいないだろう(というかいてほしくない。もし意識が向かなかった場合は過去問に取り組んでいる場合ではないので、まず問題集などで長文の基本構造を勉強してほしい)。
ただし、2文目はcallの意味なども入ってきて英語としては少し読みづらい。そこで譲歩の内容を使って、テクニックで主張の内容を読み取ろう。
(譲歩)死を定義するのは簡単と思ってるよね?
(逆説…反対の内容が来る) But
(主張)科学的には難しい場合もあるよ。
ということだ。
だから、この段落で必ず「死の定義は難しい」という話が要約に入ってくることを押さえたい。
さて、英語では「意見や立場を述べたら、次に必ず理由を述べる」という明快な論理構造が好まれる。すると次の段落には当然「なぜ死を定義することが難しくなるのか」という内容が来るので、そのつもりで読もう。
第2段落
butやhoweverといった逆接表現がなく、ひたすら順接の内容が続く。だから先ほどの「死を定義するのは難しい」という前提の主張に乗っかって読めばOK。
具体例として「脳死」が挙げられている。これはなんとなく漠然としたイメージもつくと思うが、生命維持装置が発達したおかげで、脳死の場合でも呼吸はしていて、ただ眠っているようにしか見えないこともあるだろう。このようなケースで、その患者の死を宣言することは、第1段落を引用するならば「文化的にも、宗教的にも、そして法的にも」容易とは言えない。
先ほどの第一段落に対する「理由」=「脳死の場合」がわかったところで、要約に入れ込みたい情報がだんだん揃ってきた。前半はあと一息。
第3段落
そして飛ばされがちなこの段落。やはり順接が続くから、流れに乗って読んでいけばOK。
ここでは、「脳死を診断するために国際的なガイドラインが設けられた」という話が展開される。先ほどの主張「死の定義が難しくなっている」と、どう関係するのかを考えよう。
すると、段落後半に「but〜still complicated」という逆説の箇所が出てくる。
つまり「すでに世界レベルで認められた基準が定められているにも関わらず、それでもやっぱり脳死を診断するのは複雑で難しい」ということだ。
ここまで読むと、それぞれの段落についてこのような役割が見えてくる。
第1段落…主張「死の定義は曖昧になっている」
第2段落…理由・具体例「脳死の場合、死の判定は難しい」
第3段落…主張の正当性をサポート「脳死には国際的な基準が定められているけど、やっぱり診断が難しい」
可能であれば、第3段落の内容を要約に含めた方が、意見としてより盤石になることが伝わるだろうか?
第4段落
ここからは、さらに一歩進んだ「even more challenges」について語られていく。
3文目の「life」のイメージはすぐに浮かんだだろうか?このような多義の単語の場合は、前後の比較や類推で意味をとる必要がある。
今回の場合は、ひたすら「死」の話をしてきたのだから…。当然、この「life」の意味は「人生」や「生命」ではなく、「生」、あるいは「生きていることそのもの」として捉えるべきだろう。
そして、この段落に入ってもandの順接が続くことからも、「死の定義は難しい」に続いて「これから生の定義も(いい意味でも悪い意味でも)難しくなる」という話になってきたことが読み取れるだろうか?
死の定義の時は「脳死」という具体的なケースが挙げられていた。今回はどんな時に生の定義が難しくなるだろうか?
そこで、「drugs and implants 〜 control our thoughts 〜 even change who we are」に注目したい。
読み方としては、長文読解でよくある「新情報の提示」を使っていくことになる。
「新情報の提示」とは、「読み手が驚くような情報を1番最後に持ってくる」「最後に新情報を出すことで、読み手に新鮮な驚きを与える」という英語の書き方の技法のこと。今回の段落は、最後が「even change who we are」なので、ここが最もずっしり重たく見えてほしい。
ちなみに「who we are」というのは、「私たちが誰であるか」、つまり「私たちがありのままの自分自身でいること」を指す。
脳科学と技術が今以上に進歩する中で、い病気を治すにとどまらず、感情や考えをコントロールするような薬や移植技術が生まれるかもしれない。さらに、中には自分自身がすっかり変わってしまっている状態が生まれるかもしれない。
これははたして「自分の『生』を生きている」状態だろうか?と、作者が次なる問いかけを始めている箇所である。やや抽象的な話だが、長文ではこのような抽象的な話の後には具体的な例が提示されることがほとんどなので、この時点でここまで読み込めていなくてもOK。次の段落で読み取っていこう。
本段落について要約で拾うべきは、「脳科学や技術が進歩すると、生の定義も不明瞭になる」という追加の情報部分であろう。
第5段絡
「一度死んだブタの脳細胞を科学者が再活性化させた」という話で今回の話は閉じられる。これが先ほどの「自分が変わってしまう」例だろう。
医療の現場で脳死を死と捉えるならば、ブタも一度死んでいるはず。しかしその脳が、人の手によって生き(?)返る…これこそまさに、「死とは何か?生きてるって何か?」を深く考えさせるようなエピソードだ。
それが、「This gets at〜Sanders says.」の箇所にあたる。
ちなみに、「one of the most fundamental questions we have」の取り方に関してであるが、各校で若干読み方が割れている気がする。これは自分自身のことでも考えてほしいのだが、「生きてるってこと」については人間誰もが何かしらある程度の基準を自分の中に持っていると思う。こういうのは生きてるなとか、あんな状態だったら死んでるなとか。要はまあそういうことを指していると思ってOK。
そして最後の文は「those limits」の多義語の意味をしっかり取ろう。limitは今回は「限界」ではない。今回の話を思い出せば簡単だ。
科学技術の進歩で、定義が変わりうるものはなんだったか?そう、「生や死の定義」つまり「生死の境目・境界」である。
この第5段落において、この「境界」の話は必ず要約に盛り込みたい。
要約作成
さて、これですべての段落を読み終えた。あとはキーワードと作者の主張を元に要約を作ればOKだ。
まずは自分で書いてみよう。
このとき必ず、
- 「情報の過不足がないか(特に不足がないか)」
- 「論理構成がおかしくないか(因果関係などが合っているか)」
を必ずチェックすること。
また、今回は第3段落の入れ方と、the most fundamental questionsのところは特に工夫してみよう。limitの訳も忘れずに。
書けたら、以下の解答例と比べてみてほしい。
解答
脳死を判定することは基準を以てしても難しく、死の定義が曖昧になる中、脳科学や技術のさらなる進歩は根本的な生の定義すらをも変え、生死の境目をより曖昧にするだろう。(80字)
ここまでじっくり読み込んでくれてありがとう。別のページに難問の2024年度の解説もあるので、やりこみたい人は要チェック。
長文読解の考え方は、どうしても一度解説を読んで理解しただけで体得できるものではない。このページをブックマークやホーム画面に追加して、何度も読み込み復習してもらえれば、と思う。
最後に少し宣伝。
この記事の筆者のわたらせが、二次試験や模試の勉強に役立つ「記述問題の個別添削サービス」を始めたので、内容が気になる人は以下からぜひチェックを(このSNSについてよくわからないという場合は、もちろん当ブログの問い合わせフォームから気軽にご相談していただくのでもOK)。
▶︎外部サイト:ココナラ「記述問題添削します」